はじめに 時空間が重なる建築を目指して
星野道夫の『旅をする木』の中に〈もうひとつの時間〉という一編があります。
東京で忙しなく生きる編集者がアラスカでザトウクジラのジャンプを目の当たりにし、帰 国後もふと思い出しほっとするという話です。
編集者が心打たれたのは、巨大なクジラが小さく見えるほどの 取り巻く世界の広がり。そ して、クジラが宙を舞う瞬間が今もどこかに存在するという時間の広がりでした。
〈もうひとつの時間が世界のどこかで流れていることを心の片隅に意識できるかは天と地の 差ほど大きい〉と話は締め括られます。
この話のように別の時間や別の空間を引き寄せられたら、建築はより豊かさを生み出せる ような気がします。
いまここ/ いつかどこか、複数の時間や空間が重なる建築を目指して設計をしたい と考え ています。



時空間への意識を形作ったできごと

1.手のひらのなかの宇宙 中学の理科の授業で、く宇宙がとてつもなく 広いように、私たちの手のひらの細胞ひとつひ とつにも広大な空間が広がっています。もしか したら、その中にも宇宙があり地球があるのか もしれません。私たちの宇宙だって巨人の手 のひらの細胞のひとつなのかもしれません。> と先生が話しました。それ以降ふと思い出して は、巨人の中にいる私と私の中にある宇宙を想 像しスケールを往来する旅をします。建築を学 び10年を経たのちに、先生の話はイームス夫 妻によるPowers of ten だったと知るのでした。


2.油絵具の速度 高校の美術の授業で油絵を描く機会があり、 <油絵具の固まるには長い時間がかかるので、 表面が乾いて見えても中は乾いていません。 ゴッホの絵のような厚塗りの絵の具はまだ固 まっていないのかもしれません。>と扱いを教 わりました。その話を聞いたとき、昔の偉大な 画家として遠くに感じられるゴッホの時間が、 絵の具がまだ乾いていない(=ゴッホの存在し た時間が続いている)という形で、私の生きる 時間と繋がったように思えました。
3.千年前の情景
小さい頃に曽祖母に百人一首を教わったのを きっかけに、百人一首が好きになり競技かるた のサークルに入っていました。
例えば、見上げた空に雲間から月光が落ちて綺 麗だっだとき、「秋風にたなびく雲の絶え間よ りもれ出づる月の 影のさやけさ」を思い出し ます。これは、雲の切れ目から洩れてくる月の 光の澄みきった美しさを歌った和歌です。 昔の人と情緒を共有すること、今の状況を通し てかつて描いた風景が立ち現われることに面白 さを感じ、時間旅行をしている気分になります。
46億年のメメント・モリ
-千葉県犬吠埼における海洋散骨施設の計画 -

果てしない時空へ意識を向けること
宇宙について考えるとき、自分の小ささを知る感覚が好きです。意識が私の小さな世界か ら飛び出し、果てしなく大きな世界に包まれていると気づきます。 天体の運行を用いて 体験した人が世界を発見をする建築の姿を模索したい と思いました。
過去に目を向けると天体運行を利用した古代遺跡は数多くあり、冬至や秋分など共同体で 一本の軸を共有します。これは天体運行が農耕と密接に関係し、集団として団結力を高め ることが生きることに直結していたためでした。
では、 大切にするものが様々な現代 に天体運行と関わりある建築をつくるのであれば、 人それぞれの多様な軸をつくることが必要 ではないでしょうか。
それぞれの軸による時間と場所の実感により、 果てしない宇宙の中の地球という星で 46億年続く今を生きている奇跡を意識できる のではないかと思います。
敷地を探る
犬吠埼(千葉県銚子市)
天体運行、とりわけ太陽を利用した建築物を計画するために敷地の条件を定めました。
・ 太陽の昇り沈みを確認できる よう水平線が見える場所 ・ 果てなく続く海 を意識するため太平洋に面する場所 ・太陽に関係した 象徴的意味を持つ 場所
以上の条件を満たす場所として、千葉県銚子市犬吠埼を敷地としました。
選定理由
・ 水平線がみられる ことから 太陽の昇り沈みを実感 しやすい ・太平洋に面し、視界がひらけているため 果てなく続く海 を感じる
・ 日本一早い初日の出 が見られる場所として、太陽運行の象徴的意味を持つ
また、調査を進めると犬吠埼には次のような特徴がありました。
・日本一早い初日の出が見られる場所として有名のため、元旦未明は初日の出を見る人で混 雑する
関東最東端の特異な地形 として 三方を海 に囲まれている ・およそ 1億2000万年前の白亜紀の地層 が顔を出している ・水郷筑波国定公園に含まれる 景勝地 で犬吠崎と続く君ヶ浜は関東舞子と呼ばれ多くの歌人 からも親しまれていた



犬吠埼は関東最東端に位置する 日本一早い初日の出 白亜紀の地層が見られる

1.銚子駅から2両の銚子電鉄に乗る

2. 木の葉をかき分けながら電車が進む

3.犬吠埼駅

4.駅から犬吠埼へ向かう坂道

5.犬吠埼 足元には草原がひろがる


6.岬から見た君ヶ浜 穏やかな海が広がる

7.君ヶ浜から犬吠埼を見る

8.白亜の犬吠埼灯台


9.東映のオープニングに使われる荒磯 10.君ヶ浜と違い激しい波が打ち寄せる 犬吠埼駅
前述の特徴を活かせるプログラムとして 海洋散骨 を提案します。
天体運行の魅力 は、運行が半永久的であることや周期的であることです。そこから生ま れた建築物は儀式が運行と関連付けられていて、事象が持つ意味に合わせて建築も設計さ れているため、 宇宙と人間を結ぶ結節点 としての作用があります。 事象を切り取るこ とで神秘性を伴う感動を与えるような建築がふさわしい と考えました。
神秘性を非日常体験・生や死に関わるもの、超次元的なものに感じると捉えました。また、 死者に関する行いは周期性 (命日、月命日、周忌) があり 、とりわけ、 彼岸 (春分・秋分) は太陽の運行に関係 していることに着目をしました。
そして 敷地を海辺に設定 したことから、 海洋散骨 に関するプログラムとしました。
天体運行は 弔い空間に適する
海洋散骨に まつわるプログラム 海洋散骨
海辺に計画する







海洋散骨について
海洋散骨と課題 大まかな流れ
海洋散骨とは文字通り 海に遺骨を撒いて供養する葬法 です。
社会の変化に伴い葬送文化や家族のあり方・ 価値観が多様化 したこ とにより、散骨は新しい供養方法として注目されています。
特に海洋散骨においては「知っている」「聞いたことがある」と回 答した合計の認知度が93%と高くなっています。(日本海洋散骨協 会 海洋散骨に関するアンケート 調査報告書より)
抱える問題点
散骨希望者は海が好きだから・お墓がいらないからという理由で海 洋散骨を望むのに対して、 弔う人 は「お墓参りをしたい( 手を合 わせる対象が欲しい )」と意見がありました。希望者の考え方に 弔う側の価値観が追いついていないことが見受けられます。
対象があるからこそ、人は祈りを捧げている実感を得る と いうことでした。
そこで、 残された人たちが故人を偲ぶ象徴の不足を問題と し、海洋散骨のための弔い空間を設計 しました。

出航


散骨希望車者 ・海が好き ・お墓がいらない ・体験してよかった ・子供に面倒をかけたくない
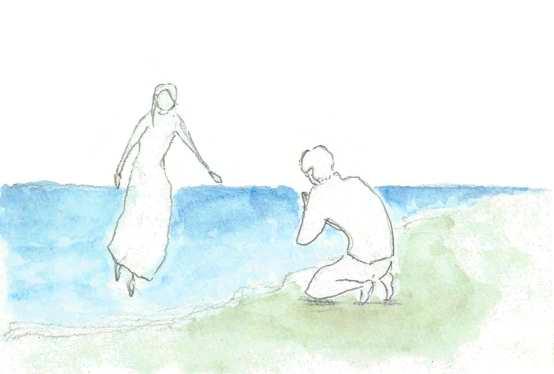
弔う人 お墓参りがしたい 手を合わせる対象がほしい



お盆や回期毎の メモリアルクローズ
形態を決める手法
1.犬吠埼を実感する

1.地形に沿わせる
等高線に沿うように形を馴染ませる


2.地形に組み込む
形を挿入することで、 地形そのものが体験をつくる
2.みんなの軸と わたしの軸をつくる

4. 軸に沿う
みんなの出来事(彼岸・初日の出) に関係する、光を通す筒をつくる

3.地形を切りとる
地層を見せ、時間の積み重ねを際立たせる



5.軸をつくる


自然光を通すと分光して虹をつくる三角プリズムを用い、 各月の日の出・日の入できまったフロア形状に積み重ねることで 日の動きを可視化しながら無数のわたしの軸を生み出す
計画と順路
散骨管理棟
弔う人のための施設 はじめに管理棟へ行き、 散骨の準備を行う
ビジターセンター
犬吠埼を訪れた一般の 方々のための休憩所
大階段
初日の出を見に来た観光 客が身を寄せ合って元旦 の朝日を観測する場

桟橋と鳥居
海へと向かう桟橋は故人 が散骨を希望した意味を 弔う人に考えさせてくれ る場
展望台
散骨した海を振り返るよ うに眺め、遠い故人に思 いを寄せる場
弔いの道
岬とつかず離れずの道を 歩くことで気持ちを整理 する一助となる
弔いの塔
故人の命日を軸とする弔 いの空間
駐車場
海中を通ることで、 行きは散骨への意識を高め 帰りは散骨された故人の気持ちになる
門を通った光が桟橋に差し込む
管理棟とビジター棟は灯台への道を 中心に対称に配置される
斎場は地下で繋がり、
外 観からは入り口のない白い箱のように見える
ちらりと見える入り口は 好奇心をそそる
灯台の周りを 弧を描くように歩く
門は彼岸と此岸を分ける鳥居のよう
地層と塔への視線
弔いの塔を中心に 円を描くように歩く
塔への視線
海 への視線
屋根がなく光が差す道 波の音だけに耳を澄ませ、 散骨の時を思い起こす
散骨した海を眺め、 故人に思いを馳せる
両サイドが開いた道は恐怖心を煽り、 死は身近にあることを思わせる
白亜紀の地層に重なった弔いの塔が見える 地球は死の積み重ねであることを想起させる
地中空間が風景を変える切れ目になる
海 への視線
塔へ向かう道は浮遊感があり 天国へ向かうような気持ちに
切り裂いた岩から初日の出見え、大階段に光が差す
大階段は普段は岸への道だが、 初日の出を見るための特等席にもなる
潮汐により変化する池
大階段から降りると時間により通ることができる
初日 の出の軸線
春分・秋分の日の出の軸線 船の通り道
春分・秋分の日の出の軸線






散骨管理棟とビジターセンター
「地形に沿わせる」

散骨管理棟は地上1階・地下1階建てとなっている。
地上には 海を眺められる待合室 、地下には粉骨室・
粉骨後の気持ちを落ち着けるための斎場 等を設けて いる。待合室から見える 海景 や斎場に落ちる 光 が際 立つように 明暗の緩急 をつけて設計した。


粉骨は葬儀の一部のように感じるため、 悲 しみに暮れられるように他の部屋から離して配置する
長く暗い通路が 内省する時間を作る
1 階平面図 S:1/600

普段は礼拝堂として人が集う

管理棟外観 斎場は地中に埋め、低く見せている

管理棟内観 奥の水盤が海と繋がり、 散骨への気持ちをつくる

通路から斎場を見る
管理棟A-Aʼ断面図 S:1/350

暗く長い通路の先には、のこぎり屋根により 柔らかい光が落ちる斎場が現れる 管理棟 A-A’断面図 S:1/350
「軸に沿う」

弔いの道入口
海中トンネル
海抜+2648
桟橋
海抜+750
散骨専用の船が停泊する桟橋。
海中トンネル は、海へ向かう人には 故人が散骨を希 望した理由を想像する場 として、陸へ向かう人には 海に舞っていった故人に寄り添う場 として計画し た。長い屋根の 桟橋 は水平線に意識を向け、ステン レスの仕上げによって 水面の揺らめきと煌めきに包 まれる ような設計とした。
みんなの軸であるお彼岸(=春分・秋分)に合わせ て計画し、 彼岸のお墓参りを兼ねたクルーズにて太 陽を拝む ことができる。





桟橋の行き来は海中を通り、 海洋散骨を選んだ故人の気持ちに寄り添う

桟橋は水面が屋根に写り込み波の揺らぎに包まれる
春分・秋分の軸に添うためお盆のメモリアルクルーズには陽が差し込む


桟橋から展望台へ向かう弔いの道は 空だけが見え る。
海にせり出した道では波の音がよく聞こえる。あえて 海への視界を遮 ることで、 波音のみに集中 できるようにした。 一人で悲しみの気持ちと向き合う ため、す れ違えるだけの道幅とした。緩やかな登り坂は息が若干上がり、その苦しさが 自分の内面に向きあうきっかけとなる。


コールテン鋼の道は訪れる度に経年変化で表情を変え、時間の経過を示す

海抜+17300
海抜+14490
海抜+11630
海抜+8770
海抜+5910
海抜+3000
海抜±0
展望台断面図 S:1/200
展望台

弔いの道の先には展望台がある。
波音の聞こえていた道とは対象的にガラスボックスで 宙に浮き 、音を遮った空
間は あの世に移動 してしまったよう。
開放的な展望台は
階段 を降りると浮遊感がある
海抜+16900
海抜+12900
散骨した場所を眺めながら、静かに故人のことを語り合う場所 として設計した。 展望台
散骨した方向を眺め、故人を思う
展望台内部から改めて散骨した海を見る 弔いの道とは対照的に波音は聞こえず、海の輝きにのみ目を向ける
春分・秋分の日の出軸線



「地形に組み込む」

海抜+17300
海抜+14490
海抜+11630
海抜+8770
海抜+5910
海抜+3000
海抜±0


弔いの道から塔を見る 塔のフロアが地層の続きのように重なる様子が見える


海抜+25000
海抜+22200
海抜+19800
海抜+16800
海抜+13800
海抜+10800
海抜+7800
海抜+4800
海抜+1800
海抜±0

ビジターセンター側からは 入 り口のみが見える



切 り裂かれた岩を通して 初日の出が大階段に差し込む
満ち引きで海水が流れ込む
弔いの塔

弔いの塔は 各月毎にフロアが分かれ ている。塔の天 井・床幅は南中高度、弧を描く床の中心角は日の長 さによって決まっている。各階に日が入りやすいよ うに、南中高度の低いフロアが下階・高いフロアが 上階になっている。
各フロアの形状の違い が、 季節毎の地球と太陽の関 係性の違いを可視化 する。

屋根 海抜+80800
6月の階 海抜+76400
7月の階 海抜+72000
5月の階 海抜+67600
8月の階 海抜+63200
4月の階 海抜+58800
9月の階 海抜+54400
3月の階 海抜+50000
10月の階 海抜+45600
2月の階 海抜+41200
11月の階 海抜+36800
1月の階 海抜+32400
12月 の階 海抜+28000
1階 海抜+25200
白亜紀の地層の上に弔いの塔のフロアが重なり、 地球は生命の積み重ねであることを想起させる

白亜紀
天頂 夏至
弔いの塔には モニュメント とし て 三角プリズム を用います。
プリズムに光が当たるように弔 いの塔の 天井・床幅は南中高度 、 弧を描く 床の中心角は日の長さ によって決定しました。
例:7月の場合
日が短く、 南中高度が 低くなる
月の最終日が 最も日が長く、 最も南中高度が高い
7 月1日の日の出 7月1日の日の入
1.三角プリズムについて
7月31日の日の入
三角プリズムは 高さ4000mm 正三角
形の1辺が300mm のものとします。
2.夏至と冬至
夏至
7月1日の南中高度 7月 8月 9月 10月 11月
3.中心角
7月31日の日の出
夏至
7月1日の南中高度
各月で最も日照時間が長い日 の 日の出 入り角度 を用いることで月毎の太陽が 照らす角度を全てカバーします。
夏至 春 分・秋分
7月1日の日の出 7 月1日の日の入
7月31日の日の入 7月31日の日の出
例:7月の場合 フロ ア N
4.天井・床の幅 南中高度が高いほど日は手前しか差さ ず、低いほど奥まで差し込みます。
これにより、各月の 南中高度が最高の 日=日が差し込みにくい日 にプリズム
7 月1日の日の出 7月1日の日の入
例:7月の場合 フロ ア N
例:7月の場合 フロ ア N
太陽が真南に来る時の角度を南中高度
例:7月の場合
7月1日の日の入
7 月1日の日の出 7月1日の日の入
月1日の日の出 7月1日の日の入
といいます。 南中高度 が 最高の日は夏
至 で、 最低の日は冬至 です。また 日照
7 月1日の日の出
7月31日の日の入 7月31日の日の出
時間 が 最長の日は夏至 で、 最短の日は 冬至 です。
フロ ア N
例:7月の場合 フロ ア N
太陽運行図
万人に重要な日其々の大切な日
に対して 最低1m分の太陽が当たる よ うに天井の高さを設定することで日に 当たる部分の最低高さを確保します。
5. 公的な軸と私的な軸
万人に重要な日其々の大切な日
例:7月の場合 フロ ア N
従来の軸
7月1日の南中高度
7月1日の南中高度
7月31日の日の入 7月31日の日の出 万人に重要な日其々の大切な日
7 月1日の日の出 7月1日の日の入
三角プリズム
万人に重要な日其々の大切な日
二至二分の朝日が入る公的な軸 = 筒状で大掛かりな装置
6.私的な軸を得る利点
7月31日の日の入 7月31日の日の出 万人に重要な日其々の大切な日
7月31日の日の入 7月31日の日の出 万人に重要な日其々の大切な日 天頂 夏至 春 分・秋分
7月31日の日の入 7月31日の日の出 万人に重要な日其々の大切な日
命日、散骨日、故人ゆかりの日etc...


設定した日時にプリズムに光が差す 故人と再会を約束しているかのように虹が落ちる

予期せぬ虹もまた、故人からの語りかけのように感じる







































































